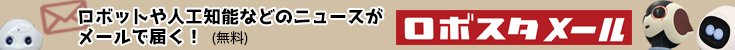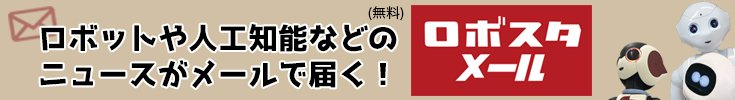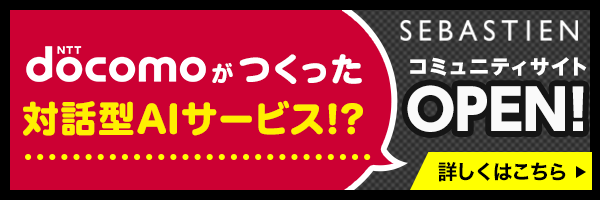家電がロボットを履く!新時代のロボット「Patin」を発表!

ロボットを履くという新しい発想
6月23日(火)、東京ミッドタウンにてフラワー・ロボティクス株式会社の新ロボット「Patin(パタン)」のプロトタイプとSDKの発表記者会見がおこなわれました。
Patin(パタン)というロボットの語源はフランス語のスケート。様々な家電製品がスケート靴のような「ロボットを履く」という新しいタイプのロボットになっています。松井代表は「これまで多くのロボットをデザインしてきた中で、ロボットの面白さを一つ一つ削いでいったところ、最終的にたった2つの面白さが残った。それが、 “動く” ということと “考える” ということだった」と語った。

松井社長は「良いデザインとは謙虚である」ということをモノを作る上で念頭に置いており、「いかにも “ロボット” というものは、家庭の中に入っていかないのではないか?」、「人の生活を邪魔しない後ろで流れているBGMのようなロボットを作りたい」という思いで今回のPatinのプロダクトデザインに至ったという。
「Patin(パタン)」は、本体と充電用ピット、そして「サービスユニット」で構成されている。サービスユニットとは本体の上に装着する家電等の部分のことで、「照明型サービスユニット」や「植栽型サービスユニット」などを取り付けることで、本体に新しい機能を付与することができる。
当日は照明用のサービスユニットと植栽用のサービスユニットの2つが発表され、デモがおこなわれた。

照明用のサービスユニットを装着

声を掛けると電気がつく

もっと優しい光にしてと言うと、温かみのある色合いになる

植栽用のサービスユニットを装着。なんか「ロボット×植物」の組み合わせは不思議で面白いですね。植栽用のサービスユニットでは、植物を育てるための様々なデータを取得することができる。
またPatinの充電用のピットはクラウドとつながっており、家庭内の行動などを情報として取得する。これまで未知だった家庭内の情報を受け取ることで、新しい市場として可能性を探っていきたいと語った。

上に装着するサービスユニットは外部のサードパーティと連携をすることで開発をおこなっていく。ハードだけでなく、ソフトウェアの開発も外部と連携していく予定でROSなどの専門知識がなくても動かせるSDKも配布される。
気になるPatinの価格は、本体・充電用ピット・2〜3個のサービスユニットをあわせて100万円程度での販売を想定。将来的に販売数が伸び生産数が上がるにつれて20万円台での販売も目指している。2016年後半から販売に踏み切る予定で、市場投入時には10個程度のサービスユニットを同時に発表できるように整えていきたいと語った。
新しいロボットの形として、市場を席巻することができるか。どれだけ多くのサードパーティと連携することができるのかという点がポイントになるのかもしれません。
ABOUT THE AUTHOR /
望月 亮輔1988年生まれ、静岡県出身。元ロボスタ編集長。2014年12月、ロボスタの前身であるロボット情報WEBマガジン「ロボットドットインフォ」を立ち上げ、翌2015年4月ロボットドットインフォ株式会社として法人化。その後、ロボットスタートに事業を売却し、同社内にて新たなロボットメディアの立ち上げに加わる。