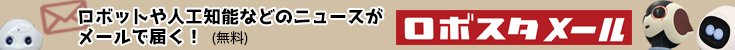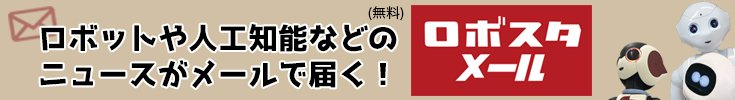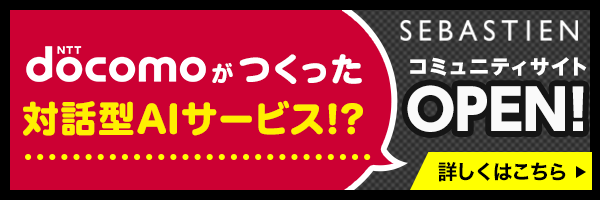ロボットビジネスの売上はぶっちゃけ想定通りですか? シャープ、タカラトミー、ヴイストンのパネルディスカッション

ロボットパイオニアフォーラム#009では、「コンシューマー向けロボットビジネスの動向を占う」と題してパネルディスカッションが行われました。
登壇者したのはヴイストンの経営企画室チーフの鷹野裕氏、シャープのIoT通信事業本部 コミュニケーションロボット事業部チームリーダー景井美穂氏、タカラトミーの新規事業部ニュートイ企画部部長の木村貴幸氏の3名、更にモデレーターは、ロボットスタートの執行役員ロボスタ編集長の望月亮輔がつとめました。

自社の紹介
パネルディスカッションの前に、まずは各社によるそれぞれ自社紹介が行われました。
ヴイストン社は大阪大学の石黒浩教授が最高顧問、ロボットクリエイターの高橋智隆氏が顧問をつとめる会社で、最近ではお二人が開発に携わったコミュニケーションロボット「Sota」(ソータ)の開発と販売で知られています。


シャープはご存じ総合家電メーカーの大手で、最近ではしゃべるAI搭載の電子レンジや掃除機なども発売、音声会話で操作できる機器を発売しています。それとやや関連して、「スマートフォンも進化がほとんどなくなり、新しいスマートフォンを開発していきたいと思ったときに、タッチパネルから音声会話で操作できるもの、動きなどがあって楽しい電話を作りたいと思い、ロボホンの開発に至りました。毎月アップデートをしていてロボホンはどんどん進化しています。またSDKを公開し、法人向けにも販売展開を始めました」と紹介しました。


タカラトミーは、90年間オモチャを作ってきた会社、500名の社員がいて、一年間に1200の新製品を子供達にとどけているそうです。トミカやプラレール、リカちゃんなどの歴史のある玩具がたくさんあります。その中のひとつ「人生ゲーム」では今年からゲームの中の職業に「ロボットクリエイター」が追加されたそうです(職業のイラストはロボットクリエイターの高橋智隆氏に似ているとか・・)。子供達の憧れの職業になるといいですね。
ロボット玩具で知られているのはオムニボットシリーズ。遡ると初代は今から30年前に登場、しかも発売された初代ロボット玩具に音声認識機能が搭載されていたと言うのですから驚きです。


ロボット購入層のターゲット
パネルディスカッションの部では「2017年からロボットを本格的に普及させていかなければならない、そのためにはどうするか」というテーマで展望が述べられました。
望月
まず「購入層のターゲット」や「製品を作る上で重視したポイントは」という質問ではじめたいと思います

タカラトミー
オムニボットシリーズは14種類で合計20万台の販売を達成しています。玩具メーカーということもあり、ターゲットとしては子供がメイン、しかしロビジュニアやオハナスなど、製品によっては7割が40歳以上という製品もあります。
その場合は、40歳代から50歳代がピークで更に高齢者もいらっしゃるといいます。
シャープ
ロボホンはスマホと同様、様々なアプリをインストールすることができ、それによって適した年齢層も異なるため、あまり購入者の年齢層を開発時に意識することはありませんでした。ただ、音声対話で直感的に使いやすい特徴があるものの、現時点では高齢者の方に購入者が多くないので(40〜50歳代が多い)、その市場を開拓していくことも重要だと考えています。

ヴイストン
Sotaは当社のホームページでデベロッパー向けに販売していますが、開発者向けなので「どのようなロボットでもご自由にどうか作って下さい」というスタイルです。そのため、年齢層はあまり意識していません。
また、最近ではNTT東日本さんと「ロボコネクト」というサービスが始まりました。OEMではフロンテオさんから発売されている「Kibiro」などがありますが、それらはそれぞれの会社の販売チャンネルで展開されています。

望月
例えば、タカラトミーのオムニボットシリーズの場合、どの製品が最も売れているのでしょうか。
タカラトミー
ロビジュニアです。5万台が売れています。また、犬型のペットロボットもシリーズでは5万台を超えていますのでこれも玩具業界ではとてもヒットしたと言えます。

望月
なるほど。皆さんにお聞きしたいのですが、現在のロボットは売れ行きの面では「ぶっちゃけ想定通り」でしょうか、それとも想定以上、もしくは想定以下の部分もありますか?
タカラトミー
ロボットスタートさんやNEDOさんなどが発表している市場の拡大予測を見ると倍々で拡大していくという想定をしている部分もありますよね。しかし、昨年度から今年度にかけては横ばいから少し拡大くらいの推移ですので、想定ほどは売れていないという感想ですね。
望月
例えばオハナスは、想定以上に売れているでしょうか?
タカラトミー
世の中に2万台くらい出荷していますが、目標と比べれば超えていないです。
望月
ロボホンは如何でしょうか?
シャープ
ぶっちゃけで言いますと想定通りではないです。目標はひとり一台のロボットを目指していますので、まだまだ注目度や認知度が足りないと思っていますが、大きな予算をとってCM展開するなどの施策もなかなかできません。
望月
Sotaについては如何でしょうか。
ヴイストン
想定より売れているとは言いがたいと感じていますが、売上げよりは開発の部分で想定外だったのが、会話部分のプログラム開発です。これがかなり大変でした。

課題解決の糸口
共通に感じている課題のひとつは、ロボットに対する消費者の期待度や認知度がバラバラだと言うこと。たとえば「ロボットでこんなことまでできるんだ」と感じる人もいれば、アニメや映画の影響でロボットに対する期待度が非常に高い人もいる、そう言った人たちから見れば、現状のロボットってまだこの程度のことしかできないのか、という評価になってしまうということです。消費者のロボットリテラシーの向上もロボット業界が積極的にやるべきことなのかもしれない、という意見が出ました。
また、ロボホンは実際に見ていただくことで本当の魅力、可愛さなどを理解して頂けるケースが多いと言います。
更には、会話のプログラム開発が難しいという話がありましたが、さらに実際にデモをする店頭などでは評価は難しくなるのも課題です。雑音が多くて人間でもなかなか聞き取ることができないような環境では、ロボットの本来の性能をきちんと理解してもらうことも難しいということです。
こうしたことから、3社ともに今後の展望に関しては、「ロボットに触れあって、機能や性能をきちんと消費者にも理解してもらえる場所、ロボットを体験することができる場所を増やすことが大切だ」という意見で一致していました。