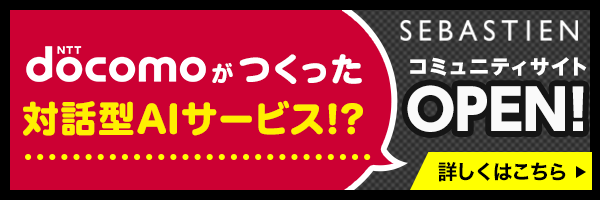「シーマンの知見を活かして次世代の日本語会話AIをつくる」シーマン人工知能研究所・斎藤由多加氏インタビュー

「ロボットとの会話にはガッカリしてばかりですよね」
シーマン人工知能研究所の斎藤由多加氏はそう切り捨てる。
私達が日常的に会話している日本語は文法に沿ったものだろうか。おそらく文法に沿ってはいないし、たいていは意識すらしていない。
斎藤氏は「日本語の日常会話には文法などない」と言う。その上で、日常会話に独特の法則があるとすれば、それを解明することで新しい文法を作るとも言う。
生活に寄り添うロボットやコンピュータ、彼らとスムーズな会話をするために必要なのはお行儀の良い日本語の文法に沿った会話エンジンではなく、日常会話の法則ではないか、と主張するのだ。
そうかもしれない。それこそがこれからの会話エンジンに最も重要な存在なのかもしれない。
斎藤氏は九州大学と連携し、日本語会話の新しい文法を生みだそうと企んでいる。

「シーマン」で日本語の独特な会話を研究し尽くした
斎藤由多加氏はゲームクリエイターで、代表作は育成シミュレーションゲームの「シーマン」シリーズだ。最初の作品は1999年7月、『シーマン~禁断のペット~』としてドリームキャストというゲーム機用に発売された。第3回文化庁メディア芸術祭デジタルアートインタラクティブ部門優秀賞や日本ゲーム大賞ニューウェーブ賞、小学館DIME誌トレンド大賞などを受賞し、その先進性が大きな話題となった。
先進的だったのは、コントローラのマイクを使い、ゲーム内の謎のキャラクターであり毒舌な「シーマン」と会話する点だ(シーマンの声は斎藤由多加氏本人によるもの)。会話を通じてシーマンは学習して成長するし、あるいはユーザーが話した秘密まで握るという、実に奇妙な未来感が漂っていた。

しかし、この頃のゲーム機はネット接続もなくスタンドアローンで動作していた。現代のように膨大な情報からなるクラウドのデータベースに繋がっていたわけではない。それなのにシーマンとの会話は当時のゲームユーザー達に受け入れられた。その理由は絶妙な「会話の間」や「受け応え」だっただろう。しかし、実はそこが本質ではなく、会話の内容にポイントがあると斎藤氏は言う。
斎藤(敬称略)
人間の会話の一番の関心事って「当事者が関わっている」ことなんですね。例えば「アメリカの映画産業って最近は・・」なんて話題よりも、「お前って最近評判悪いよ」って話題の方が、誰もが一気に耳を傾けて、詳しく話をしたい、聞きたいと感じるものなんです(笑)。

どうしたら会話が楽しくなるのか、ヒトが興味を持つ会話を生成できるのか、その上でユーザが話していることを正確に理解することが、会話ロボットやスマートスピーカー、人工知能コンピュータにとって次に必要になることだと考えています。
シーマンは誕生したばかりの頃(幼魚は「ギルマン」と呼ぶ)、言葉を覚えていないので会話ができない。しかし、少し育ってくると「イイスルカギキ」という意味不明な言葉を連発するようになる。当時ゲームをプレイしていたときは、ギルマンは適当な単語を連発しているのかとばかり思っていたが、これは実はある日本語を逆回転させたもので、意味のある言葉だった。シーマンとの会話は言葉のやりとりを練りに練られた結果、生み出されたものだった。斎藤氏はシーマンの続編で、北京原人語という架空の言語作りにも挑戦している。
シーマン人工知能研究所をつくった意味
編集部
ここシーマン人工知能研究所を設立されましたが、シーマンの新作を制作するためではなく、日本語におけるAIの研究開発をする研究所だと聞きました。
斎藤
そうです。「シーマン」という冠をつけた理由は3つあります。
ひとつは「エンターテインメントであることを忘れない」ためです。最新技術は製品になるところの戦略がしっかりしていないと消費者がガッカリするものになってしまいます。最近登場しているロボットの多くもガッカリさせられるものが多いですよね。ヒトが会話をするには情報の伝達や共有のほかにエンターテインメントであることが重要なんです。
ふたつめは、研究所の成り立ちに関係するのですが、政府の助成金などの公的な資金援助を受けられなかったので、有志の人たちが集まって知恵と資金をしぼって草の根の底力だけで運営していこうと思っているからです。「下町ロケット」のように(笑)。その意思が込められています。
みっつめは、とはいえ消費者の皆さんには応援して欲しいという気持ちがあります。お馴染みである「シーマン」というイメージがあった方が親しまれやすく、気軽に応援してもらいやすいのではないかと考えたのです。
ただ、私達自身が注意しなければいけないのは、消費者の方々に「新しいシーマンを作るために設立した」という誤解を与えてはいけないということです。私達は、新しいシーマンを作るのではなく、シーマン開発の知見やノウハウを活かして、今までにない全く新しい「フロントエンドの日本語音声会話システム」を作るために設立したのです。
全く新しい「フロントエンドの日本語音声会話システム」とは
斎藤
ロボットやコンピュータが人間と会話する時代がやってきていますが、私達が作るフロントエンドの日本語会話システムの役割は2つあります。
ひとつは人間と会話をして、人間の言っている言葉を数値化し、クラウドにある人工知能システムや専用の質疑応答システムに受け渡すインタフェースです。すなわち、すべてのロボットや端末に組み込むことができ、質疑応答システムやコグニティブシステムと連携することができる日本語会話システムです。

編集部
例えば、コミュニケーションロボットに組み込んだり、IBM Watsonのフロントエンドで会話をするシステムになり得るという意味ですね。
斎藤
そうです。世の中には既にすぐれた質疑応答システムやFAQ応答システムはたくさんありますが、私達の会話エンジンはそれらと競合しません。むしろ協力して共存し、お互いを高め合うシステムです。
多くのシステムはユーザーからの質問を理解して、それに対して最適な回答を返すようなシナリオが作られています。シーマンの基本的なしくみも同じです。現在では、ディープラーニングを使って機械学習することで膨大なシナリオをコンピュータが学習し、自律的で高精度な会話ができるようになってはいます。
しかし、賢いはずの質疑応答システムが実務であまり機能できないのはなぜでしょうか。いくら膨大なシナリオや豊富な回答を持っていても、ユーザーがシナリオ通りに質問しなかったり、ユーザーが聞きたいことを正確にコンピュータが把握できないために正しい回答を出せないのです。
私達が開発するフロントエンドの日本語音声会話システムは「ユーザーが何を聞きたいのかをはっきりと理解した上で質疑応答システムに渡す」という役割を担います。
編集部
シーマン人工知能研究所が開発しようとしているのは、高精度な質疑応答システムや情報を提供するシステムと協業する、ユーザーの矢面に立つ会話システムの部分ということですね。
斎藤
優秀な質疑応答システムを開発したのだけど、日本語の多様性に対応できていないためにユーザにとって満足度が高い会話ができない、できそうにないという企業がパートナーになりうると感じています。私達は日本人の会話を長年研究し、シーマンを通して培った知見を活かし、口語での会話を熟知したシステムを提供したいと考えています。
編集部
なるほど。シーマン研究所の日本語会話システムのもうひとつの役割とはなんでしょうか。
斎藤
もうひとつは、相づちを打ったり、受け返の言葉を返したりするような、バックエンドの人工知能システムやビッグデータでは、決して答えが返って来ない会話にローカルで対応することです。
質疑応答システムを例にしましたが、ヒトとの会話は質問や命令だけではなく、「今日ふられちゃったよ」とか「やる気なくすよな」と言った回答のないものもたくさんあります。しかし「今日ふられちゃったよ」と言えば「またかよ、今年に入って何度目だよ」とか「やる気なくすよな」と言えば「どうしたの? 会社でなにかあったの?」など、ヒトは受け返す言葉を期待して話すこともあります。質疑応答システムでは正解のないものは返せませんが、私達の日本語音声会話システムがそこも担当します。相づちをうったり、受け返しながら、ただ聞いてあげることでも、親和性を高めてエンタテインメントに近付くものになると思っています。相談する相手はヒトにとってとても重要で親しみやすい存在たりえますから。
編集部
そこでも、シーマン開発のときの研究が役立つわけですね。
ABOUT THE AUTHOR /
神崎 洋治神崎洋治(こうざきようじ) TRISEC International,Inc.代表 「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」(日経BP社)や「人工知能がよ~くわかる本」(秀和システム)の著者。 デジタルカメラ、ロボット、AI、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数(アマゾンの著者ページ)。