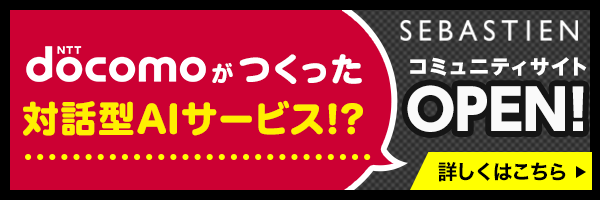NTTドコモの新AIエージェント「my daiz(マイデイズ)」はアマゾン・グーグルに勝てるのか

NTTドコモが本日発表したAIエージェント「my daiz(マイデイズ)」。新商品・新サービス発表会の冒頭で発表があったことからも、ドコモが同サービスにかける意気込みの高さが伝わってくる。
本記事では先ほどの発表会レポートに補足する形で、「my daiz」とは一体どのようなサービスで、どのように役立つのか。そしてそのビジネスモデルや競合優位性をご紹介していく。
「my daiz」とは

「my daiz」は、ユーザー一人一人の行動や状況を学習し、ドコモおよびパートナー企業の提供するエージェントであるメンバー(後述)が、それぞれのユーザーにあった情報やサービスを適切なタイミングでスマートフォンやタブレットに届けるサービス。
スマートフォンやタブレットの「アプリ」として提供され、「my daiz」という豆腐のようなはんぺんのようなキャラクターと画面上でテキストまたは音声によって「対話」ができるほか、アプリケーション上で様々な情報を受けとることができるようになる。

スマホアプリはAndroidおよびiOSに対応しており、Androidの場合にはスマホのホーム画面にも「my daiz」のキャラクターが出現する。ドコモ以外のキャリアユーザーも、dアカウントを取得しアプリをインストールすれば使うことができるが、他キャリアのAndroidユーザーのみ、アプリ提供は今年の秋になる見込みだ。
my daizの追加機能「メンバー」とは

今回の話が単に「ドコモがAIエージェントを発表した」という発表に留まらない理由が、この「メンバー」にある。
メンバーとは、AIエージェント「my daiz」を進化させる追加機能のこと。
AmazonのAlexaでいう「スキル」ようなものと、LINEのLINE@アカウントを組み合わせたようなものだ。外部のパートナー企業がmy daizに「メンバー」として追加機能を提供することができるようになり、例えばマクドナルドがオススメの商品を紹介したり、WEBメディアはニュースを配信できるようになる。

ユーザーは好きなメンバーを追加することで自分好みに「my daiz」のアプリをカスタマイズすることができる。初期パートナーとして33の自治体・企業が並び、合計で56のメンバーが準備されている。
活躍の場はスマホだけじゃない
この「my daiz」が活躍するのはスマホアプリとしてだけではない。先日ソニーモバイルから発表されて大きな話題を呼んでいるスマートイヤホン「Xperia Ear duo」にも対応しており、耳元に装着してタップするだけで「my daiz」を呼び出すことができる。こういった外部デバイスを接続することで、スマホ画面を開かずとも「my daiz」の機能の恩恵を受けることができるのだ。

またNTTドコモの「シンプルマイク01」からも「my daiz」を呼び出すことができる。発表会の質疑応答では「スマートスピーカーを発売する予定はあるか」という質問が飛んだが、同社代表取締役社長の吉澤和弘氏からは「今のところNTTドコモがスマートスピーカーを作る予定はない」とし、「メーカーの皆様にぜひパートナーになって頂き、開発していってもらいたい」と呼びかけた。
「my daiz」は競合に勝てるか
Amazonからは「Alexa」、Googleからは「Googleアシスタント」、Appleからは「Siri」、LINEからは「Clova」と世界中のIT大手が自社のAIアシスタントを開発している。Facebookの「M」の後継と目される「Marvin」、マイクロソフトの「Cortana」、サムスンの「Bixby」、アリババの「AliGenie」、SK Telecomの「NUGU」…と挙げたらキリがない。
そんな群雄割拠の中、ドコモはどのように戦うのだろうか。「機能面」・「キャリアとしての立ち位置」・「メンバー」という3つの側面から考察してみた。
習慣の把握で「先読み」

「my daiz」のもっとも注目すべき機能は、GPSと時間帯を組み合わせることで行動習慣を把握し、先読みを行う機能である。「この人はどの電車に乗って、どこに通勤しているのか」を把握することができる。つまりスマホに搭載されているからこそ、その人の習慣の一端を把握することができるのだ。
この情報を元に「my daiz」は電車の遅延情報や天気予報などを、ユーザーが調べずとも教えてくれる。また、アラーム機能とも連携することで、「この人はいつも7時に起きているけども、電車が遅延しているから6時45分に起こそう」と考えて、早めにアラームを鳴らしてくれたりもする。
これらは常に持ち歩くスマホを持っているから把握できる情報であり、こういった行動の先読みが外出先でも役立つのだ。ぜひ使ってみたい機能である。
しかし気になるのは個人情報の扱い。ドコモによれば「これらの情報を仮にパートナーなどの第三者に提供する場合にも、個人が特定されない形で提供する」という。もちろん位置情報の提供についてはスマホの端末側でオフにすることもできる。
もう一つ機能面として付け加えるならば、ドコモには過去にしゃべってコンシェルで培ってきた対話技術もある。対話の要素技術においても国内でトップレベルだ。もしもユーザーが、AIアシスタントに対話性能を求めるのだとしても、それに応えていくだけの技術力はあるということだ。
キャリアとしての立ち位置
ドコモの2019年度の携帯電話のLTE(Xi)契約数は5550万と予想されている(FOMAの契約も含めると7637万)。キャリアだからこそできるのが、キャリアアプリとしての提供。一部の機種に関しては、夏モデルでプリインストールアプリとして提供するよう現在調整中だ。AmazonがAlexa搭載のスマートスピーカーを全世界で数千万台出荷していると言われているが、ドコモはいきなりそれに相当するほどのユーザーの携帯に「my daiz」を提供できる環境が整っている。

しかし気になるのは、Googleアシスタントの存在だ。スマホを持っていないAmazonのAlexaとは明確に差別化ができているが、Androidの標準機能として搭載される「Googleアシスタント」とどのような差別化を図っていくかはポイントになるだろう。
「メンバー」は急増するか

AI音声アシスタントの大きな核となるのがサードパーティ製のスキル・アプリであり、my daizにおけるメンバーだ。この数が少なければアシスタントは追加機能が不足して魅力に欠け、ユーザー離れが進んでしまう。
今もっとも成功しているのはAmazonのAlexa。米国では3万以上のスキルが開発され、日本国内でも発売4ヶ月で265スキルから600スキルへとその数を倍以上に増やしている。
このようにスキル数を増やすためには、サードパーティが「このAIアシスタントにスキル・メンバーを提供することに価値がある」と感じさせることが必須であり、Alexaはアマゾンエコーの普及台数を伸ばすことでAlexaの影響力を強くし、パートナー企業にAlexaスキル開発のメリットを感じさせている。同じく、NTTドコモの強みはここになる。NTTドコモの契約者が皆使うという訳ではないが、今後「iコンシェル」のユーザー(2018年3月末時点で700万人弱)や、「しゃべってコンシェル」のユーザーに対して告知していくほか、dマーケットでおすすめしたり、公式HPやしゃべってコンシェルのTwitterアカウントでも情報を発信していく。つまり、ユーザー数が桁違いのスピードで増えていく可能性が高いのだ。
サードパーティとしても、提供するのであれば、その影響が大きいプラットフォームに提供したいと考えるのが自然だろう。そして、それはそのまま「my daiz」の魅力に繋がっていく。
また、スマホ画面で機能を提供していくため、サードパーティはURLをユーザーに対して送ることができる。これは既存のWEBサービスとの連携もはかりやすく、サードパーティとしても嬉しいことかもしれない。
このように「my daiz」が国内においてそのユーザー数を増やす可能性は高いと見られる。「my daiz」を搭載したデバイスの開発も推奨されており、このデバイス数が増えていくことでさらに影響を強くしていくことは可能だ。
my daizのビジネスモデルは?
「my daiz」のマネタイズ手法の一つは、有料機能の提供である。天気・気象や道路交通情報・ルート案内といった基本機能をアプリ内で見たり、対話によって情報提供を受けるのは無料だが、それらの通知を受ける機能や先に示したアラーム(早めに出発アラーム、予定リマインド)は有料。ただこれらも100円/月で利用することができるため、ドコモの規模からすると、そこまで大きなマネタイズポイントにはならなさそうだ。
そこで見込まれるのが、メンバーの有料プラン。2018年度中はパートナーのメンバー提供には費用はかからないが、来年度以降は未定だという。LINE@のようにプランがいくつか用意され、そちら側でマネタイズする方法は考えられるだろう。

様々な側面から「my daiz(マイデイズ)」を見てみたが、「どのようにGoogleアシスタントとの差別化をはかっていくか」「有力な”メンバー”を揃えられるか」という2点が直近の課題になっていきそうだ。
ABOUT THE AUTHOR /
望月 亮輔1988年生まれ、静岡県出身。元ロボスタ編集長。2014年12月、ロボスタの前身であるロボット情報WEBマガジン「ロボットドットインフォ」を立ち上げ、翌2015年4月ロボットドットインフォ株式会社として法人化。その後、ロボットスタートに事業を売却し、同社内にて新たなロボットメディアの立ち上げに加わる。