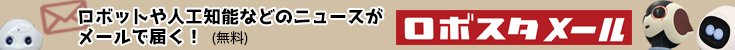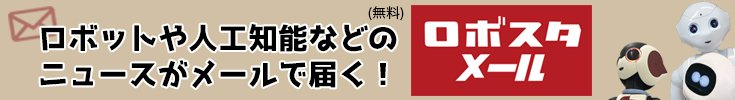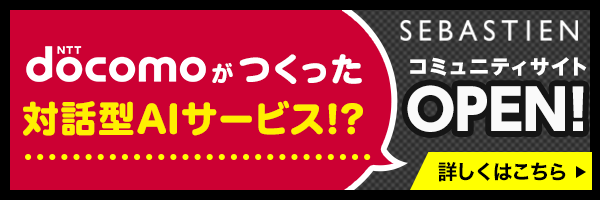ココロくすぐるロボ 「ROBITA」 を企画しよう!【ROBITA PROJECT -DAY1- 】

8月12日(水)、渋谷のloftworkにて「ココロくすぐるロボ”ROBITA”を企画しよう ROBITA PROJECT-DAY1-」が開催されました。
今回は、全3回に渡るROBITA PROJECTの初回。ユカイ工学株式会社の代表を務める青木俊介さん、そしてTRYBOTS代表の近藤那央さんがロボットの企画に関する講師をおこない、その後 “愛されロボット” を企画するワークショップが開催されました。
ユカイ工学さんは、コミュニケーションロボット「BOCCO」の開発や、爆発的な話題を呼んだコミュニケーションツール「necomimi」の商品化を手がけるなど、企画力・開発力に長けた会社。そしてロボットいきもの工房TRYBOTSは、ペンギン型ロボット「もるペン!」の開発をおこなう、注目の大学生チームです。今回はこちらのイベントのレポートです。
▽ ROBITA PROJECT
http://www.opencu.com/2015/07/robita-project/
ユカイ工学流「愛されロボットの作り方」

まずはユカイ工学・青木さんから、愛されロボットのデザインについてのレクチャーです。

企画について、セグウェイ開発者の考え方を引用し、「現状の問題をストックし、問題のスープを作っていく。そして問題がテクノロジーと交わったときに発明が生まれる」という発想方法を教えて頂きました。

また、100年前の住宅の写真を用いて、「人間が心地よいと感じるものは長い間変わっていない。テクノロジーが進化しても、ロボットに対して可愛いと思うポイントは変わらないはずである」と説明。
たしかにこういった視点から見ると人間は保守的ですよね。100年後も今も可愛いと思うロボットに大差はないのかもしれません。

続いてロボットとはなにかについて。青木さんの考えるロボットは「人とカンケイを作る機械」のこと。

「定義上は、” センサー・モーター・アクチュエイターがあって、ある程度自律的に動くもの ” ですが、その定義に当てはめると自動改札機もロボットになりますし、人によっては自動販売機だってロボットと言うかもしれないです。つまり、皆さんがロボットだと思ったものはロボットなんです」

次にかわいさとはなにか。カーネギーメロン大学のロボット研究所所長も務めた金出武雄先生が定義したかわいさとは「予測可能な予測不可能性」。このようにプログラムを書けば可愛く見えるといった考え方を示したもので、「ワンパターンではなくて、完全なランダムでもない状態が可愛い」ということを示唆している。
日本の工学者。京都大学工学博士。専門はコンピュータビジョン、ロボット工学。1985年にカーネギーメロン大学教授、1992年~2001年には同大学のロボティクス研究所の所長を務める。2001年に産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究ラボ長併任となり、2003年からデジタルヒューマン研究センター長(センターは後にデジタルヒューマン工学研究センターに改称)。クオリティ・オブ・ライフ(QOL:Qolity Of Life)にも着目し、2006年にはカーネギーメロン大学に生活の質工学研究センターを設立、センター長に就任する。
出所:Wikipedia「金出武雄」を一部改変

AIBOのしっぽやファービーの耳は愛されポイントの一つ。揺れがデザインのポイントになっているようです。

最後に、ユカイ工学が開発し現在DMM.make ROBOTSから販売中の「BOCCO」はどのように生まれたかについて。

BOCCOを企画した当時のコンセプトが公開されました! 当初から「座敷童のようなロボットを作りたい」と考えられており、こどもを意味する「wappa(わっぱ)」や、関西弁で言い換えた「bon(ぼん)」なども名前の候補に挙がった中で、東北弁の「bocco(ぼっこ)」が採用されたそうです。

BOCCOは、「鍵っ子を助けてくれるようなロボットを作りたい、留守番電話を置き換える存在にしたい」という思いで企画されたそうです。貴重な裏話をお話いただきました!
近藤那央さんが考える愛されロボットとは?

近藤那央さんは1995年生まれの19歳。高校時代にペンギンロボットの開発チーム「TRYBOTS」を結成し、その後はロボット関連の様々なイベントやメディアにも多数出演しています。現在は慶應義塾大学環境情報学部に在学中。「スマホのように生活の中にロボットが溶け込んでいる未来を作ること」を目指している。

TRYBOTSでは、もるペン!というペンギンロボットを開発。現在TEPIA先端技術館で展示がおこなわれています。

近藤さんは、母校の小学校でおこなわれた「子供たちが考える友達になりたいロボット」という図工の授業のエピソードを披露。そのときの子供たちが考えたロボットはどれも、「背丈が2mほどの巨大なものでカラフルなロボット」だったそう。そのときに近藤さんは「子供たちに愛されるロボットには”不器用そう” “カラフル”という特徴があるのではないか。また大きさは関係ないのではないか」と感じたようです。

また、もるペン!を様々なイベントで展示してみて、子供たちから人気を集めることがわかったことから「 “触れる” ということと、”素材を生かした自然な動きをすること” も愛されポイントなのではないか」と考察。

そして、「なんでも出来るのではなくて、人間と同じようにときには失敗してしまったり、物を食べたりトイレに行ったりするような “一見無駄な行為” によっても親近感や愛情が湧いてくるように感じます。ペットの場合には、病気にかかってしまったときの、”治す” という行為で愛情が湧いてきたりします。ロボットも壊れてしまったときに修理をしてあげるという過程が実は重要なのではないでしょうか」
「出来杉くんのようになんでも出来てしまうロボットよりも、のび太くんのように少しダメなロボットが家にいると、なんか可愛いと感じるのではないか、と考えています」と、近藤さんが考える愛されロボットのポイントを語ってくれました。
みんなで愛されロボットの企画を考える

イベント後半、いよいよワークショップがスタート! 参加者は「企画」「開発」「デザイン」といった得意分野ごとに分類され、各チームに最低一人ずつが振り分けられていきます。1チーム5〜6名で、全部で6つのチームに分かれました。

各チームごとに、「誰が使うロボットなのか」「どんな場所で使われるロボットなのか」というキーワードを書き出していきます。

次にそこから5つずつのワードを選び、マトリックスを作っていきます。

マトリックスの交わった点に、課題を書き出し、そこに必要なロボットを考えていきます。

最後に具体的にロボットを描きながら、機能や愛されポイントを考えます。
事前に青木さんと近藤さんに、愛されポイントなどを整理して頂いたこともあり、参加者皆さまの考えるスピード感が半端なかったです。

そしてチーム内で各々が企画したロボットを発表し、代表者を選出。各チームの代表者による発表がおこなわれました。「冷蔵庫の中の腐ってしまった食料を食べてくれるロボット」や「30代の独身女性に合コン必勝法を授けてくれるロボット」、「方向音痴の人のために作られたのに歩くのが遅いロボット」など、どのアイデアもとてもユニークな愛されロボットでした。すべてご紹介できないのが本当に残念。

ワークショップ終了後には壁に貼られた30以上のロボットの企画書を見ながら懇親会。未来のロボットについて話しながら飲むお酒は最高でした!
第2回目からの参加もOK

次回、第2回目となる「ROBITA PROJECT -DAY2- <ロボ企画書を元に、立体物を作ろう>」は、8月24日19:30〜、同じく渋谷のloftwork COOOP10Fにて開催されます。今回参加できなかった方も、第二回目から参加することが可能です! 参加費は1500円。申し込みは下記ページから行ってください。
▽ OBITA PROJECT DAY02 – OpenCU.com
http://opencu.com/events/robita-day02

今回のイベントは、loftworkのロボット班の皆様による企画でした。今後も様々なロボット関連のワークショップやハッカソンなどがおこなわれるようです。それらの情報は「robo.org」で発信される予定ということなので、是非こちらのサイトもチェックしてください。今後のloftworkロボット班の動きは要注目です!
▽ Robo.org WEBページ
http://robo.org/
ABOUT THE AUTHOR /
望月 亮輔1988年生まれ、静岡県出身。元ロボスタ編集長。2014年12月、ロボスタの前身であるロボット情報WEBマガジン「ロボットドットインフォ」を立ち上げ、翌2015年4月ロボットドットインフォ株式会社として法人化。その後、ロボットスタートに事業を売却し、同社内にて新たなロボットメディアの立ち上げに加わる。