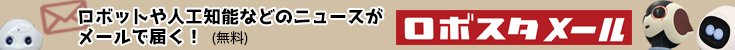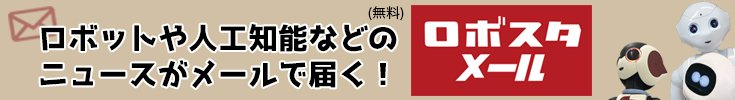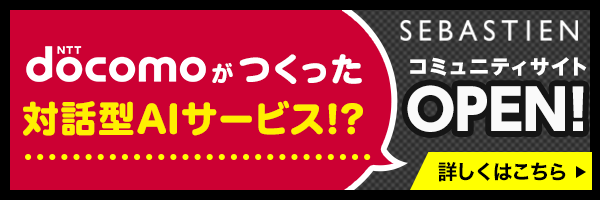「電源を入れないPepper」と一緒にアイディアソン&劇的プロトタイピング

10月20日(火)、東京・秋葉原のアーツ千代田3331にて、「Pepper App Challenge 2015 winter」に向けたアイディアソンが開催されました。講師は株式会社ハイレグタワーのウメムラタカシさん。ハイレグタワーは舞台・映像出演に関するマネジメント業をおこなう会社で、その中でウメムラさんはロボットの舞台出演に関するマネジメントをおこなっています。

「劇的Pepperアプリプロトタイピング」というイベント名の通り、今回のアイディアソンは普段とは少し違う角度からおこなわれた模様です。一体どのような内容になったのでしょうか。
第一部 アイディアソン
▽ アイディアソンの進め方
1.「日常生活で困っていること」を考える

アイディアソンでよくおこなわれる導入と同様に、まずは個々人で日常で困ったことを絵に描いてグループ内で発表していきます。
2.Pepperアプリを考える

そして1で出た「日常生活で困ったこと」を解決するPepperアプリを個々人で3つずつ考えていきます。
しかしこれではユーザーが必要とするアプリなのかを判断することはできません。また、アイディアを考える元になる情報も少ないため、アイディア出しも容易ではありません。そこでグループワークで別の角度からアイディアを考えていきます。
3.ペルソナ・共感マップ
先ほどのアイディアを一旦忘れて、今度はグループごとにペルソナと共感マップを用いて「Pepperと暮らす人」のユーザー像を作りあげていきます。ペルソナとはマーケティングで用いられる技法で、年齢・性別・出身地・職業・1日の過ごし方・人生のゴールなど、様々な情報を詳細に設定していくことでリアルなユーザー像を明確にしていくことができます。
また、共感マップを使い「そのユーザーはどんなことを普段考え、何を感じているだろう」「何を目にし、何を聞いているだろう」ということを考え、ユーザー像をさらに鮮明にしていきます。
そしてユーザー像が明確になったところで、そのユーザーは「Pepperに何をしてもらいたいのだろう」という要望を考えていきます。

その結果、一つ目のグループでは「Pepperに励ましてほしい」という要望が、二つ目のグループでは「誰も話を聞いてくれないのでPepperに話を聞いてほしい」という要望が抽出されました。
4.ブレイン・ライティング

続いて、ブレイン・ライティングという手法を用いて、3で出た要望を解決するためのPepperアプリ(特技)をグループ毎に考えていきます。ブレイン・ライティングを活用した進め方は以下の通りです。
① 2分間で一人一枚の画用紙に3つのアイディアを書いていきます(付箋にアイディアを書き、画用紙に貼っていく)
② 画用紙ごと隣の人に回していきます
→①②を4回繰り返します。すると、それぞれの画用紙に12個のアプリアイディアが羅列されました。一人で1枚の画用紙に書くよりも、隣の人に回しながら書いていくことで、他の人の意見からインスピレーションを得ることができるようです。
5.アイディアのカテゴリー分け
全部で12個×人数分生まれたアイディアを、近いアイディアごとにカテゴリー分けしていきます。
6.ドットシールで投票

カテゴリー分けができたところで、ドットシールを使って投票していきます。シールには黄色・赤・緑の3種類が用意されており、実行がカンタンと思われるアイディアには黄色いシールを、効果が絶大だと思われるアイディアには赤いシールを、新規性があり奇抜なアイディアには緑色のシールを貼っていきます。
7.順位付けとバタフライテスト

グループごとにシールの多いアイディアを5つ選び、それをグラフにまとめます。グラフの縦軸には効果の高さを、横軸には難易度を置くことで、アイディアの特徴を視覚化していきます。緑色のシールがたくさんついているものは、中でもよりオリジナリティの高いアイディアということです。
8.グループごとにアイディアを決定
話し合いの上でプロトタイピングをおこなうアイディアを決めます。最初に個人で生み出したアイディアよりも、よりユーザー視点にたったアプリ案が選出されたようです。
第二部 プロトタイピング
通常のPepperハッカソンなどでおこなわれるプロトタイピングでは、Pepperの電源を入れて、開発ツールのコレグラフを使ってアプリを作っていきます。しかし今回のプロトタイピングは即興劇というまったく違う手法でした。
即興劇
今回のプロトタイピングでは、グループごとに「そのアプリも持ったPepperがいる空間ってこんな感じだよね」という、即興劇をおこなっていきます。リビングにPepperがいるとどうなるか、食卓にいるとどうなるか。利用シーンやセリフを考えて、グループごとに即興劇をおこないます。

一組目のアイディアは、Pepperユーザーの女性に良い男性を紹介してくれるというアプリ。ユーザーはPepperに「励ましてほしい」という要望を持っているため、元気付けるという意味で良い男性を紹介してくれます。ポイントは付き合うところをゴールにせずに、あくまで紹介するということ。良い男性を紹介してもらえるだけで、楽しい気分になって元気が出てくるのではないか、と今回のアプリアイディアに至りました。
二組目のアイディアは、Pepperが話を聞いてくれて、同じニッチな趣味を持つ海外の人とつなげてくれるというものでした。こちらのグループが作ったユーザー像は「誰も話を聞いてくれないので、Pepperに話を聞いてもらいたい」という要望を持っており、メインの機能にPepperが相槌を打って話を聞いてくれるという機能と、追加機能としてその話の内容を英語に翻訳し、海外向けに発信してくれるという機能を持っていました。
どちらのグループも即興劇にすることで、実際の会話のイメージを具体化したり、必要な機能があぶり出されたりと、仕様書や企画書では表面化できない課題が抽出できたようです。
各班の即興劇を全員で観劇し、質疑応答の後、今回のイベントは幕を閉じました。イベントに参加したエンジニアの額賀さんは「エンジニアはアプリの仕様作りにまず目が行きがちですが、使用時の空気感を大切にするという考え方が勉強になりました。社内でのアイディア出しの際にも参考にしたいです。」と満足度の高さを語りました。また、アルデバランアトリエスタッフの梅田さんは「即興劇は完成したアプリをもっと使いやすいものにしたいというときにも使えるのではないか。アイディアソンのやり方は一つ一つに良し悪しがあるため、様々なやり方を知っていることは大切なことだと感じました。」と感想を語りました。
「Pepper App Challenge 2015 winter」への応募期間はあと僅か。これから急ピッチで作る方も、既存のアプリをより良いものにしたいという方も、今回の手法をぜひ参考にしてみてください。
ABOUT THE AUTHOR /
望月 亮輔1988年生まれ、静岡県出身。元ロボスタ編集長。2014年12月、ロボスタの前身であるロボット情報WEBマガジン「ロボットドットインフォ」を立ち上げ、翌2015年4月ロボットドットインフォ株式会社として法人化。その後、ロボットスタートに事業を売却し、同社内にて新たなロボットメディアの立ち上げに加わる。