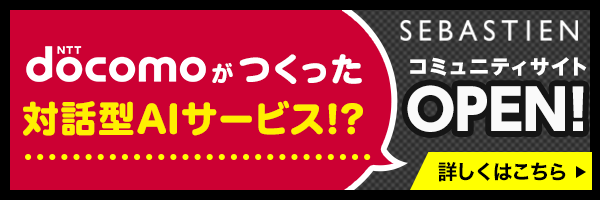「2025年の市場規模は1.5兆円」ライフロボティクス尹氏が語る、協働ロボットの未来

12月11日にTKPガーデンシティPREMIUM秋葉原で開催された「ロボットパイオニアフォーラム#009」に、協働ロボットを手がけるライフロボティクス代表の尹 祐根(ユン・ウグン)氏が登壇した。今回の記事では、その模様の一部をレポートする。
尹氏は、2001年から産総研の研究員に加わると、2007年に国立研究所発ベンチャーとして協働ロボットの開発を行う「ライフロボティクス」を創業した。そして、直近の1年間で15億円もの大型資金調達を行なっている。尹氏によれば、昨年までは外部からの出資を受けてこなかったという。
尹氏
2007年に会社を設立してから、2014年あたりまでは協働ロボットを誰も理解をしてくれませんでした。2008年にリーマンショックがあり、世界的に人が余っている中で「人手不足を補うためにロボットが働く」と言うと「バカか」と言われていました。
しかし私は当時の人口減少の資料を見て、協働ロボットは将来絶対に必要になると考えていました。
近年ようやくアメリカや欧州が協働ロボットの推進を始め、後追いする形で日本政府も協働ロボットに注目をし始めました。
協働ロボットの市場は2015年には150億円程度と言われていますが、2025年には1兆5000億円にも拡大すると言われています。

尹氏
協働ロボット(Collaborative Robots)は、世界的には「Cobot」と呼ばれるのが主流になってきました。産業用ロボットとは違い、安全柵が必要がない、人と一緒に働くロボットアームです。産業用ロボットは導入が難しく安全性が低いものですが、協働ロボットは導入が簡単で安全性が高いものです。人にぶつかったら止まるという技術はもちろんのこと、協働ロボットに必要な技術が導入されています。
なぜいま協働ロボットは世界的に注目を集めているのか。コストが安くなり、技術力が高まったこともありますが、それだけではありません。
安い人件費の国でものづくりをするという仕組みが近いうちに終わってしまう可能性が高まっているからです。中国の人件費が高騰してしまい、工場は東南アジアに移されるようになりましたが、その東南アジアでも人件費は高騰し始めています。インターネットの普及いわゆる情報革命によって、賃金の上昇スピードが上がっているのです。
そのため、先進国を中心に、国内の工場で低コストでモノを生産するという仕組みづくりが始まっており、そこで活躍するのが協働ロボットというわけなんです。
さらに日本では別の現象により需要が高まっている、と尹氏は続ける。
尹氏

東京にいると実感がないかもしれませんが、地方では少子高齢化に伴って過疎化が深刻化しています。そして、過疎地にある工場では、労働者が集まらないという事態が発生しているのです。
また、工場内では、一般の方々が想像している以上に人による手作業(繰り返しの単純作業)が必要な工程が多いんです。例えば、エビグラタンの上に乗せるエビは人が一個一個置いていたりします。
このような仕事は人がやるべき仕事ではありません。私も学生時代に同じようなバイトをしていたことがありますが、時間が経つのが非常に遅くてとても辛い。そして、10年働いても給料が上がっていく仕事ではないのです。
ではなぜこれらを未だ人間がやっているのかというと、生産ラインが頻繁に変更されているところでは、据付の産業用ロボットを導入できなかったり、導入するために工場のスペースを拡張しなければいけなかったりするからです。
その点、協働ロボットは、導入が簡単でスペースも取りません。簡単に工程を覚えさせることができ、女性でも高齢者の方でも安全に一緒に働くことができます。
特に、私たちが開発した協働ロボット「CORO」は、肘がないため危険性も少なく、怖さがありません。アームを振り回すのではなく、アームが伸びる。この技術力は世界的にも高く評価されています。
このライフロボティクスのCOROは、名だたる大手企業を中心に急ピッチで販売が進められている。協働ロボットが活躍するのは工場だけではない。安全で、導入が簡単なため、サービス分野でも使用することができるのだ。
Forbes Japanから技術力ナンバーワンと認められた今でさえ、顧客の要望を満たすためにロボットアームの地道な研究を進めているというライフロボティクス。同社はこの先も、より革新的な協働ロボットを生み出していくことだろう。
あなたの隣で「CORO」が働く未来も間近に迫っているのかもしれない。
ABOUT THE AUTHOR /
望月 亮輔1988年生まれ、静岡県出身。元ロボスタ編集長。2014年12月、ロボスタの前身であるロボット情報WEBマガジン「ロボットドットインフォ」を立ち上げ、翌2015年4月ロボットドットインフォ株式会社として法人化。その後、ロボットスタートに事業を売却し、同社内にて新たなロボットメディアの立ち上げに加わる。